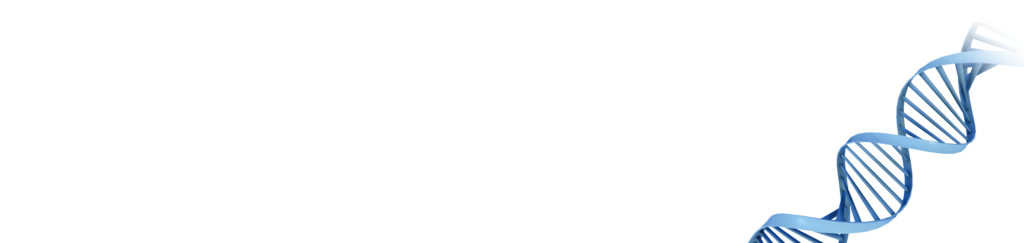高橋 龍三郎
中期社会から後期社会への社会変容について明らかにするために、以下の項目について調査研究を進める計画である。
- 中期環状集落が半族を基盤とする集団の対立的構造体であることを証明するために、多くの環状集落の構造について検討する。同時に引き続き北米北西海岸部、南米原住民社会(アピナエ族、セレンティ族)について文献調査する。
- 中期社会が双系制社会であることを東南アジア地域および南米Ge族などの調査から明らかにする。特にその出自のもつ有利性について検討する。
- 後期集落の構造分析を進め、ゲノム解析との整合性について検討する。
池谷 信之
- 黒曜石原産地推定
縄文時代中期から後期にかけての黒曜石流通の変化と社会構造の関係を検討するための基礎作業を継続する。縄文中期では、分析資料が不足している房総半島南部出土の縄文中期の黒曜石を原産地推定し、縄文後期では分析資料がきわめて少ない大宮台地と茨城県南部の黒曜石を原産地推定する予定である。 - 土器胎土分析
東海西部~南関東の古窯址出土資料と在地土器を大量に蛍光X線分析することによって地域ごとの化学的特性の傾向を把握し、その結果とこれまでの中期土器の分析結果と比較する。
植月 学
データ集成の対象地域を千葉県の太平洋岸や東京湾西岸(埼玉、東京、神奈川)に拡大するとともに、埋葬、供犠など個別の出土事例に着目した集成と出土状況や部位組成の検討をおこなう。
年齢構成に関して中期の、特にシカのデータが不足しているため、新たな資料の探索、再調査に着手する。特にイヌについては食用の可能性を解体痕の有無から調査する。
イノシシ、ニホンジカ出土量の時期的変化の要因を明らかにするためにストロンチウム(Sr)同位体比からみた産地・狩猟域の変化を検討する。
太田 博樹
千葉県市原市の3つの貝塚(祇園原、菊間手永、西広)から出土した人骨について、遺跡内および遺跡間での血縁関係を核ゲノム情報をもちいて解析する。加えて、草刈貝塚出土人骨についてもディープ・シークエンシングを進め、得られた情報を使って遺跡内の血縁関係を解析する。
近藤 修
- 内耳骨迷路形態の計測と分析
- これまでにCTデータを取得した複数の縄文遺跡の内耳骨迷路形態について、線計測と3次元形態計測を行い、2つの手法間の一致度を確認する。
- 集団間の形態差について分析する。
- 遺伝的指標(ミトコンドリアDNAパプロタイプ、核DNA情報による近縁度)との比較をおこなう。
- 千葉県草刈貝塚、権現原貝塚出土例の分析
草刈貝塚の個体埋葬例、権現原貝塚合葬墓例を整理し、人骨の出土情報(位置、部位)と、内耳骨迷路形態情報を整理、統合する。
藤田 尚
2024年度は、2023年度の古人口学研究の方向性を日本の古人骨を対象に行いたい。できれば縄文時代中期から後期の遺跡が望ましいと考え、該当する遺跡を探すことに注力するが、過去社会は極めて短命であり、それは国境に無関係であるともいえる。従って、韓国ほか世界の古人口復元が可能な遺跡からの人骨を鋭意調査していく。併せて考古寄生虫学による寄生虫感染症が、縄文時代人の健康にどのような影響を与えたか、そして、遺伝的に均質な集団とならないような、縄文時代人の知恵(科学に裏打ちされたものではないとしても、ヒトは自然と会得するものである)についての解明も行っていく。
米田 穣
千葉県で作成した高精度Sr同位体比地図について、動物骨と比較して縄文時代への応用可能性を検証する。また、加曽利貝塚と向台貝塚について狩猟域の推定を行い、遺跡事の活動範囲を推定する方法を検討する。人骨についても、千葉市や市原市の縄文時代の資料でサンプリングを実施し、Sr同位体比の測定を行う。
埋葬個体と解体個体における骨組織での微生物浸食について、加曽利塚で見出された差異が一般的な傾向なのか、他の遺跡での検証を進める計画である。また、焼骨や集骨などで、二次葬が軟部組織が腐敗する前、あるいは腐敗後のどちらで行われたか、検討する、DNA解析などを実施している縄文時代の集骨について、社会構造を解読する際の基礎的な情報として、集骨や二次葬の意義を検討する。