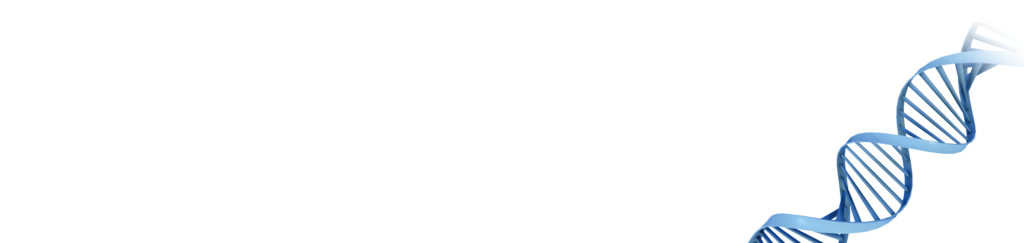2022年4月に文部科学省科学研究費(基盤研究A)に採択され、新たに縄文時代の社会に関する研究に着手することになりました。課題は「縄文時代中期から後・晩期への社会変動に関する考古学とDNA分析の共同研究 (2022-2025)」です。前回の科研(基盤研究A 課題名:縄文時代の氏族制社会の成立に関する考古学と集団遺伝学の共同研究 2018-2022)から引き継ぎ、縄文時代の社会変動の解明を目指すものです。従前の考古学に馴染みの深い方は初めて耳にするかもしれませんが、考古学プロパーではない、ゲノム解析や炭素―窒素同位体分析などの最新の生命科学を盛り込んだ文理融合の研究課題です。
前回の研究では、縄文時代の中期から後・晩期への社会変動に焦点を合わせ、中期環状集落の解体後、後期、晩期の氏族制社会の成立について解明を目指しました。その大きな契機となったのは、1995年に公表された茨城県取手市中塚貝塚の一括再葬土坑から検出された後期人骨のmtDNA分析の結果でした。科学博物館の篠田謙一教授らの研究によって、何と、縄文時代後期には親族構造の上で単系出自の母系制社会が登場していたという、大変ショッキングな内容でした。それは考古学プロパーの研究では、到底導き出すことのできない成果でした。これに対する考古学の受け止め方は多様なものでしたが、生命科学の世界的な進捗と考古学への積極的な応用に対応するために、考古学でも受け入れ態勢を整える必要性が認識されました。
代表者の高橋は縄文後期社会の解明を目指しており、中期の環状集落の解体から後期集落への変遷、それと歩みを共にする墓制の変革、儀器などの発達など、後・晩期に新たな展開を見せる考古資料に注目し、この時期に大掛かりな社会変動があったことを推測しておりました。
ただ考古学的な仮説は、それだけでは証明することが出来ず、他の手法によって証明する必要があります。その方法として、DNA分析や同位体分析、形質人類学的研究、古病理学研究をはじめ生命科学から支援を受ける必要があります。しかし、それらの最新科学がいかに優れた方法であるといっても、モデルを一度に一括で証明できる方法ではありません。ひとつずつ丁寧に証明しながら、証明を積み重ねて進むほかありません。
そこで考古学の各資料を検討し、中期から後期にどのような社会変動が起こったのかについてモデルを構築し、仮説となるシナリオを描く必要があります。前回は、トーテム制に基づく氏族制社会が後期に成立するプロセスを描き出し、実際にmtDNA研究で証明できた個所がありました。また人間だけでなく、動物を含めた同位体による食性分析でも大きな成果を収めてモデルの確かさを証明できた個所もあります。
この間、聖マリアンナ医科大学、千葉県教育委員会、千葉県埋蔵文化財センター、千葉市教育委員会、加曽利貝塚博物館、千葉市埋蔵文化財センター、市原市教育委員会、市原市埋蔵文化財センターなどの調査・研究機関の皆様には資料を提供していただくなど、大変お世話になりました。改めて感謝申し上げます。
今回の研究は、それらの研究成果を背景にして、さらに縄文中期、後期社会に遡って新たな研究計画を立てております。それらの方法に加え古病理学、動物骨や黒曜石・土製品の蛍光X線分析などの分析科学を有機的に組み合わせて縄文時代最大の社会変動について解明したいと考えております。
代表者 早稲田大学文学学術院・教授 高橋龍三郎