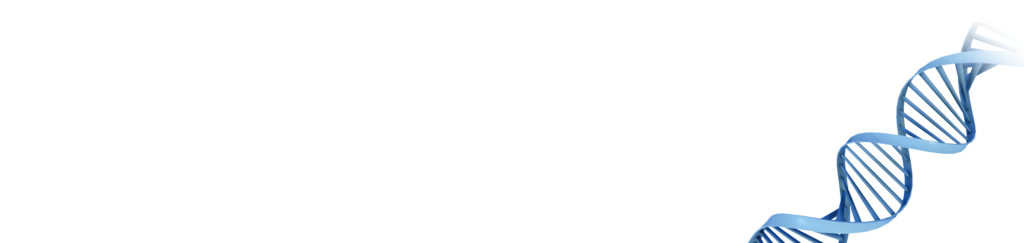高橋 龍三郎
科研の最終年度に当たるので、考古学データを分析し以下の1~3の事項を検討する。
- 中期環状集落の構造理解、構成原理の把握に努める。それを世界の民族誌から補強し、なぜ彼我で共通した親族構造、出自制度があらわれるのか理論的に解明し、縄文時代中期から後期の社会変動の理解に応用する。現在、日本の学会では、この社会変動は気候環境の悪化を前提に理解されているので、その説の妥当性について検討する。主な眼目は、環境の悪化がなぜ直接に親族構造、出自体系、婚姻システムの変動を必要としたのかについては、全く理論的に説明できていないので、そのプロセスについて検討を加えたい。そのためには以下の要件を検討する
(1)中期環状集落の構造と構成原理について検討を進め、双分的、非単系出自(双系制)が成立するか否かを考古学的に検討する。
(2)そのうえで中期の草刈貝塚(環状集落)の廃屋墓人骨のゲノム解析の結果を待ちながら、改めて草刈貝塚の構造について考える。 - 後期社会が単系出自(母系制)であるとの学説を市原市内の3遺跡(西広貝塚、祇園原貝塚、菊間手永遺跡)の人骨のゲノム解析による追加調査から再検討する。その結果を踏まえて、市内3遺跡間の人的交流(婚姻)等について研究を深める。併せて、それらの遺跡における出自と墓制の原理を明らかにする。
- 後期社会がトーテミズムに基づく氏族制であることを、動物形土製品などのシンボリズムからさらに追及する。また氏族ごとに異なる物質文化を保持したことを明らかにする。
以上の計画実施状況については学会(日本考古学協会第91回総会セッション発表:2025年5月25日筑波大学)で公表する予定である。また論文や書籍、講演などで公表する。
池谷 信之
「黒曜石組成型」の内容をさらに充実させるために、特に埼玉県東部の縄文後期遺跡出土黒曜石の原産地推定を重点的に実施する。
その結果をもとに長野県星糞峠の黒曜石採掘址から得られた黒曜石の流通ルートを想定する。この作業には原産地推定結果とともに、AIによる原産地からの移動コストモデルも援用する。星糞峠原産地は千曲川水系に属するため、その黒曜石は北廻りで主に群馬~埼玉方面にもたらされたと予想される。採掘址から出土した加曽利B1式と、群馬~埼玉方面の同型式土器を詳細に検討し、星糞峠まで遠征して黒曜石を獲得したヒトの故地を推定したい。
植月 学
引き続き、通常の食料残滓とは異なる「埋葬」や「儀礼」にかかわる特異な事例の集成を進める。また、集成データのより詳細な検討もおこなう。具体的には個体数の算定、遺跡内での位置や人の墓域との関係などの出土コンテクストの吟味、動物遺体の属性(年齢、性別、部位組成、被熱の有無)などである。儀礼の認定についても一旦は報告書の記載に従ったが、認定基準に検討の余地がある。焼骨、焼骨片の解釈についても研究史の整理をおこないつつ、儀礼との関係を見直していく。以上の作業を通じて、縄文時代のトーテミズムの存在を動物考古学的に検証できるのか、本研究課題の他の分野の成果との整合を図りつつ、明らかにしていく予定である。
太田 博樹
当初、サンプリングの方針として、DNA残存率が高いことが期待できる側頭骨を採取した。しかし、このサンプリング法の場合、分析を行わない古人骨の数が一定数あることになる。血縁解析において、解析方法によっては原理的に1~2親等の検出を基本として互いの血縁関係を推定していく。このため、墓域の全ての個体を分析しない限り、全体的に血縁関係を低く見積もる可能性がある。このため、分析対象とするサンプル数を増やして、上述の解析を再度実施し結果の精度を高める。
近藤 修
内耳骨迷路形態の計測と分析
- これまでにCTデータを取得した複数の縄文時代と弥生時代の遺跡出土の内耳骨迷路形態について、3次元形態計測を行い、以下の点について検討する。
- 現代日本人、縄文人、弥生人の集団間の形態差を分析し、形態距離と遺伝距離のデータを比較する。
- 遺伝的指標(ミトコンドリアDNAパプロタイプ、核DNA情報による近縁度)がわかる個体との対比をおこなう。
中門 亮太
2025年度は、北海道・北東北を含めた配石遺構を含め、後期前葉の大規模環状列石から晩期に至る配石遺構の系譜を整理する。
また、東北地方における大規模環状列石は、中期後葉に関東・中部地方の配石遺構や環状集落の影響とする見方があり、配石遺構の伝播の実態を探るための民族調査を行う。民族調査では、過去に確認した配石遺構と氏族組織の関係を追跡調査し、配石遺構に関する聞き取りを行う。
藤田 尚
2025年度は引き続き縄文時代人の平均寿命の問題に取り組むと同時に、感染症の流行や近親婚による集落規模の変化を古病理学的見地から考察することと並行し、廃屋墓などの考古学的証拠からの検討を行う。
米田 穣
分析が遅れている向台貝塚と曽谷貝塚の動物骨について、歯エナメル質のSr同位体比を測定し、種領域の推定を実施する。遺跡間のモノとヒトの交流関係と狩猟域の共有・排他的利用について検討する。またヒトの歯エナメル質のSr同位体比における海産物摂取の影響を検討した上で、加曽利貝塚などでヒトの交流を復元を試みる。
骨組織像における微生物浸食の有無について、貝層の内外など微細な堆積環境に着目し、土壌微生物による浸食の多寡に起因する可能性を検証し、埋葬犬が儀礼的な供犠である可能性を検討する。