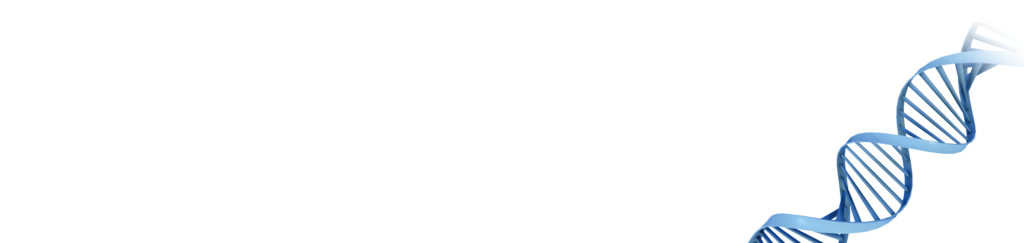高橋 龍三郎
本研究課題の遂行に当たり、期間中に主に次の項目について調査研究する。
A:中期社会に関する項目
- 中期環状集落の特性について
①半族あるいは胞族による双分的性格について実際に関東・中部地方の勝坂期集落を分析する。土器の動物形突起に注目し、半族(胞族)内での分有のし方を明らかにして、実際の居住区分と動物形象との相関を解明する。
②勝坂期の集落構成の一般性を解明し、中峠期以降の集落変遷に至る過程を明らかにする。
③加曽利E1式以降の集落構成の双分的あり方を解明する。
これらを通じて、想定される非単系(双系)出自の親族構造を明らかにする。広場を挟んで対置する世帯との通婚(限定交換)が想定されるので、その実態を明らかにする。 - 中期環状集落の解体に係る研究
①解体プロセスの実態をできる限りミクロな視点で描き出す。
②半族(胞族)が解体する具体的様相を把握する。 - 解体後に移動した集団の新たな居住について
①市川市権現原遺跡およびそれ以外の遺跡を分析し、限定交換の婚姻の実態を明らかにし、それが終焉に向かう兆候を探る。環状集落の真の解体を見極めるためである。 - 双分制に関する民族誌を検討する。北米北西海岸の民族誌は、とくにハイダ族、トリンギット族の半族(胞族)を中核とする双分制は参考になるので、民族誌と現地の考古学データを照合し、Raven半族とEagle半族の成立過程を検討する。それを縄文中期の双分制研究に援用する方法論を検討する。
- プロト・トーテミズムに関する検討。市川市向台貝塚17号土坑検出のイノシシ2頭が人と同じ食餌を与えられて育ち、その後に供犠された食性分析の結果が得られているので、イノシシがトーテムとしてある集団のシンボルとなっていたことが判明している。そこで中期社会との関係性を整理して、後期社会に至るトーテミズムの生成過程を解明する。
- 非単系出自(双系出自)社会の民族誌的検討
中期社会が単系出自以前の非単系(双系)出自と想定しているので、東南アジア地域に発達する同社会について民族誌研究を行う。 - 草刈貝塚の廃屋墓に見る親族形態の実態を明らかにするため、ゲノム解析のデータと照合する。太田博樹教授との連携をはかり、草刈貝塚における親族構造と婚姻のあり方を検討する。
B:後期社会に関する項目
- 後期社会の親族構造の解明
①西広貝塚のmtDNA分析で明らかになった母系制原理の考古学的検討を通じて、2遺体を並行させる特殊な埋葬法について、他の遺跡(例えば古作貝塚、祇園原貝塚)の事例を検討する。リネージの様相が把握できるか検討する。
②市川市の多遺体再葬土坑の事例を分析し、親族構造を導き出す方策を検討する。
③トーテムごとの遺跡間の緊密な連絡を見るために、市原市祇園原、西広、菊間手永遺跡などの共通性を検討する。
④人骨のmtDNAデータと照合して後期遺跡間の関係性、特に婚姻関係を明らかにする。 - 動物形土製品の性格の解明
①動物形土製品の種類ごとに胎土分析(蛍光X線解析)を実施し、トーテム集団ごとに特定の胎土を用い、土製品を製作した痕跡を把握する。これは以前に土器胎土とは異なる動物形土製品独自の胎土があり、土器とは異なる次元で製作されていたことが判明している。
②後期遺跡ごとに遺物を観察し、帰属するトーテム集団を明らかにする。 - 後期墓制の検討
下太田貝塚等の埋葬墓地を検討し、頭位方向や埋葬区画の在り方に、親族関係が投影されているのかを検討する。これについては千葉県域に多数の事例がある。 - 交易網の検討
①黒曜石の産地同定と、交易ルートの特定。帰属するトーテム集団ごとに原材料の配給ルートが異なっていたらしいので、蛍光X線分析の結果と照合してクランごとにどのようなルートが開発されていたかを解明する。
②貝輪等の製作地と消費地の関係が明らかになっている場合の、両者を繋ぐ論理の解明。おそらく同じ氏族同氏の緊密なルートが予想されるので、トーテムを介在して両者の関係を読み解く。
池谷 信之
- 縄文時代中期から後晩期にかけての黒曜石流通の変化
南関東から東海東部にかけての地域では、縄文時代中期前葉になると各集落で保有する黒曜石は神津島産が圧倒的多数を占めるようになる。つづく中期後葉ではしだいに信州に原流域をもつ河川の上流側から信州系黒曜石が増加する。しかし後期以降は原産地推定が実施された事例の地域的偏りが大きく、南関東全体の傾向を示すことが難しいため、良好な資料を選んで原産地推定を実施していく必要がある。
千葉県市原市を対象としたこれまでの研究では、中小の河川ごとに流通する黒曜石原産地が異なることが明らかになっており、この傾向が他の地域においても確認できるか否かが当面の課題である。 - 縄文時代後晩期の土製品の胎土分析
縄文土器の胎土分析には、混和される砂粒の鉱物を分析・同定する鉱物学的分析と、粘土の化学的な性質を分析する化学的分析がある。このプロジェクトでは蛍光X線分析装置を用いた化学的分析によって、千葉市内野第1遺跡出土の動物型土製品に一般の縄文土器とは異なる粘土が用いられていることを明らかにした。内野第1遺跡はこの地域の中核的な集落として機能していたと考えられているため、ここで製作された動物型土製品がトーテムを共有する周辺集落に分配されているかどうかが今後の課題となる。
植月 学
本研究課題のテーマである縄文時代中期から後・晩期の社会変動に関して、動物資源利用の面でどのような変化が起きており、それが何に起因するのかを解き明かしていく。本研究課題が主な対象としている下総台地ではこの期間に貝類、魚類、哺乳類の対象種や年齢構成、サイズなどに顕著な変化が起きていることがすでに明らかになっている。対象期間内では遺跡数にも増減がみられることから、人口動態の変化が推察される。こうした人口動態の変化が動物資源利用のあり方にも影響しているという見通しを持っているが、その因果関係に関する検討はいまだ十分でない。そこで、本研究では同位体分析による狩猟圏・入手域の変化の検討など新たな手法も組み合わせながら、より多角的に動物資源利用の変化を明らかにしていく。さらには他の研究分担者との連携を通じて、ヒトの食性や病理、系統の変化、あるいは石材など他の資源獲得様式の変化との比較検討をおこない、最終的には動物資源利用における変化が、どのような社会変動を反映しているのかの総合的な理解に結び付けることを目標とする。
太田 博樹
古代ゲノム解析による遺跡集団の親族構造の解明
縄文社会を科学的に読み解く上で、1つ1つの遺跡(集落)を構成した人々の親族構造を明らかにすることは研究の第一歩となる。遺跡から出土した古人骨は、生物学的データにもとづき血縁関係を復元する最良の材料である。従来こうした人類学的分析は、形態に刻まれた情報に頼る他なかった。しかし近年、古人骨からDNAを抽出し分析する技術を開発・発展した。本研究は、古代ゲノム解析の技術を縄文遺跡から出土した人骨どうしの血縁分析に応用する試みである。
近藤 修
頭蓋形態、とくに内耳骨迷路と大臼歯形態より埋葬個体間の分析を行う
千葉県草刈貝塚遺跡出土の頭骨について、内耳骨迷路と下顎大臼歯についてCT撮影をおこない、それぞれの形態特徴を計測する。計測方法としてはこれまで経験のある線計測に加え、大臼歯歯冠の溝形態を抽出するための楕円フーリエ分析、エナメル象牙境界などのランドマークによる幾何学的形態測定をもちいる。比較資料としては、現代日本人と東京大学博物館所蔵の縄文時代人骨を利用する。これらより、性差、集団差について、さらには埋葬個体間の関係について分析する。
中門 亮太
主に以下の2点から、縄文時代後晩期社会の考古学的事象を整理し、共同研究者による分析結果を解釈するための土台を構築する。
- 土器の民族考古学的研究
氏族社会における土器づくり民族誌の成果では、土器型式の流通・広域分布には、親族組織のつながりや、儀礼体系の共有など、祭祀・儀礼のあり方が影響する可能性が指摘できる。縄文時代後晩期社会の様相について、遠隔地出土土器や異系統土器に注目し、その背景にあるモノ・ヒト・情報の動きを探る。 - 配石遺構から見た縄文時代後晩期社会の研究
縄文時代中期中葉以降、東日本では配石遺構が多く見られるようになる。これらを全て一連の流れに位置付けることができるかは、未だ議論が分かれるところであり、配石の構造や構築時期、遺跡内の位置などを分析し、その機能や社会的意味について考察する。
藤田 尚
縄文時代の氏族制社会の形成および変遷について、古病理学の領域から研究を進めている。古病理学は日本およびアジア地域での研究者も少なく、一般への認知度も低い。しかし、現代人であれ、原始時代人であれ、その大半はケガや病気で命を落としていたはずであり、過去社会にどのような疾病があったのか、平均寿命はどの程度だったのか、主要死亡原因はどのようなものだったのか、などは極めて重要な課題であると言える。また、3年前(2020年)からのCovid-19の世界的パンデミックで、世界の政治、経済、社会の変容が生じたのと同様に、過去社会においても病気は人々の生活や社会の在り方を激変させたであろう。極端な場合、国の興亡さえ左右したはずである。
このような視点から、縄文時代の氏族制社会の形成や変遷には、縄文時代人を悩ませた「病気」とその病気から派生したであろう受容せざるを得ない社会変容が生じていたと考えられる。縄文時代人は、現代科学的知識は持ち合わせていなかっただろうが、我々以上の優れた経験知から、自らの社会を変容させうまく対処していたのであろう。
いずれにせよ、縄文時代人の古病理学的分析は極めて困難を伴うが、欠くべからざる研究領域であり、本科研研究で鋭意その解明に全力を尽くしていく。
米田 穣
同位体分析を用いた縄文時代の社会構造に関する研究
本研究では、同位体分析を遺跡から出土する人骨と動物骨に応用して、縄文時代の社会構造に関する実証的なデータを提供する。
- 人骨の炭素・窒素同位体比に加えて放射性炭素年代を測定し、同時代性の高い人骨の間でみられる食生活の個人差を検討する。人骨の放射性炭素年代は、食生活において海産物が占める割合によって、放射性炭素濃度が低い海洋リザーバの影響をうけるため、安定同位体比に応じて個別の海洋リザーバ効果を補正して、それぞれの個体で較正放射性炭素年代を推定する。とくに合葬墓や多数遺骸集積土坑などで親族関係が想定されていた個体間で生前の食生活を比較することで、埋葬位置と集団における消費単位の対応関係を明らかにする。これらの情報は古代ゲノムから推定される近縁関係から親族構造を復元するための基礎情報としても活用する。
- 埋葬された動物骨と解体・散乱した動物骨の同位体分析
古人骨で食生活の復元に用いた炭素・窒素同位体比は、雑食性のイノシシやイヌの食餌を推定することも可能である。とくに埋葬されたイノシシやイヌの食性にヒトによる給餌の影響があるか、検討する。狩猟採集民である縄文人にとって、狩猟のパートナーであるイヌは大切に埋葬されると考えられてきた。一方、縄文時代早期の上黒岩岩陰や小竹貝塚などで出土したイヌ骨では食餌が異なる個体が混在していることがわかった。縄文時代のイヌの役割には狩猟犬だけではなく、動物儀礼のために特別な扱いをうけた個体が存在する可能性を検証するために、同一遺跡から出土したイヌ骨において埋葬骨と散乱骨の炭素・窒素同位体比の比較を実施する。あわせて、骨組織像の違いから埋葬方法の違いを検討する。 - 人歯エナメル質に含まれるストロンチウム同位体と酸素同位体比をもとに、遺跡外から混入してきた個体の検出と、その出身地推定を試みる。そのために、千葉県内における詳細なストロンチウム同位体比地図を作成する。歯エナメル質のストロンチウム同位体比は幼少期に育った場所の地質環境を繁栄するため、婚姻などで移住してきた個体を検出することが可能である。この方法を応用するために、植物が吸収することができるストロンチウムの同位体比について地図を作製することが必要である。本研究では、千葉県中央博物館の協力のもと、千葉県内で採取された植物標本を網羅的に分析し、機械学習を用いた新手法で詳細な地図を作製することを試みる。この値と遺跡から出土した人骨や動物骨のエナメル質の同位体比を比較して、この方法の有効性を検証し、集団間の交流の復元に活用する。