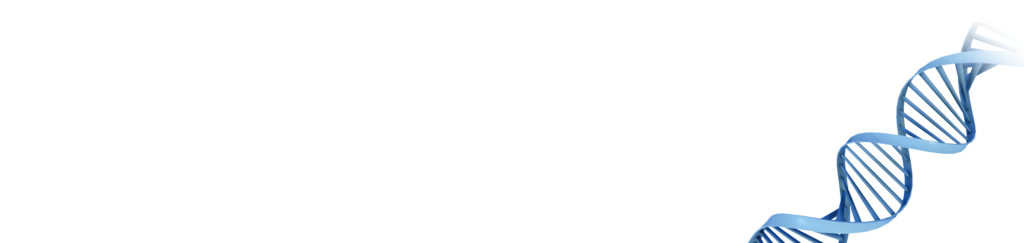高橋 龍三郎
中期社会から後期社会への社会変容について明らかにするために、以下の項目について調査研究を進める計画である。
- 中期環状集落の双分制原理の解明
関東・中部地方の環状集落を、出土した土器にみる動物形象把手から分析し、イノシシ、トリなどシンボルが半族(胞族)制度と関係するのかを検討する。またこれについて海外の文献資料を調査する(特に北米北西海岸諸族)。 - 中期社会の出自に関する研究
中期社会が非単系出自(双系出自)であると措定しているので、廃屋墓等の人骨資料について形質研究からの支援を受けて検討する。また草刈貝塚の廃屋墓のゲノム解析のデータと照合しながら検討する。また非単系出自(双系出自) について海外の文献資料を検索する(特に東南アジア諸族)。 - 後期社会の墓制研究
後期社会が母系制社会であることを西広貝塚人骨のmtDNA分析から判明しているので、2体一対で埋葬された女性の位置づけを他遺跡の事例を集成して検討する。この作業により、親族原理あるは出自の在り方が葬制に反映することを証明する。 - 中期プロト・トーテミズムの研究
中期のイノシシ供犠に示されるプロト・トーテミズムについて追加の資料を探索し、実態を解明する。これについては炭素-窒素同位体の研究からの支援を受ける予定である。 - 動物骨の比較に基づくトーテミズム研究
後期の貝塚出土の動物骨と比較して 動物の供犠と埋葬(再葬)について検討してトーテミズムとの関係性を明確にし、トーテム集団と動物の関係性を明確にする。氏族社会の出現過程を解明する。動物骨研究からの支援を受ける予定である。 - 縄文時代中期、後期の流通に関する研究
黒曜石、土製品、土器胎土の蛍光X線分析からの支援を受けて、中期、後期の有からの違いから物資の流通過程(交易)の違いについて検討する。
池谷 信之
- 黒曜石原産地分析
南関東~東海東部にかけての既存の黒曜石原産地推定事例を収集、さらに池谷が分析して未報告となっている分析例を加えて、中期から後期にかけての黒曜石流通の変化を検討する。昨年度の市原市域の検討により、後期になると中小の河川流域ごとに黒曜石の入手先(原産地)が異なることが示された。検討対象を南関東~東海東部に広げ、水系と黒曜石の流通ルートの関係、さらにその変化を明らかにする。 - 土器胎土分析
昨年度は沼津市愛鷹山麓に立地する丸尾遺跡において、ほぼ同じ割合で共存する曽利Ⅴ式(中部系)と加曽利EⅣ式(関東系)の胎土(鉱物)分析を実施した。結果はこの系統の異なる土器型式に異なる粘土が用いられていることが明らかとなった。これは愛鷹山麓に異なる地域の集団が移住し、かつ共存していることを示唆している。今年度は長野県内の中期環状集落内で共存する異系統の土器(曽利式・唐草文系・加曽利E式)の胎土分析を行い、環状集落が異なる出自をもつ集団によって形成されている可能性を検討する。
植月 学
- 研究活動計画の概要
- 市川市向台貝塚、曽谷貝塚など、縄文時代中期~後期の貝塚遺跡を対象に、動物遺体の種組成、性比、年齢構成、部位組成などを比較する。
- 他地域の事例として、太平洋岸の銚子市余山貝塚(後期)の動物遺体分析を実施し、東京湾岸との比較をおこなう。
- イヌ、イノシシ、シカなどのSr同位体比を測定する。
- 予想される研究成果
- 縄文時代中期から後期にかけての漁撈・狩猟活動の構成、あるいは狩猟圏の変化からみた生業戦略の変化の解明
- 太平洋岸との比較による東京湾沿岸の漁撈・狩猟活動の地域的特徴の把握
- 中期から後期にかけての生業戦略の背景にある社会変化の考察
太田 博樹
下記の研究を実施する計画である。
- DNA残存量の少ない検体に対するキャプチャー法シークエンシングの実施
- 検体全体について可能な限り深度を上げるシークエンシングの実施
- 得られた核ゲノムDNA配列データにもとづく遺跡集団内・集団間の血縁度算出
- 核ゲノムおよびミトゲノムにもとづく集団内の血縁解析
- 核ゲノムおよびミトゲノムにもとづく集団間の血縁解析
近藤 修
- 内耳骨迷路形態の計測と分析
画像解析ソフトをもちい、線計測データを収集し、個体間の距離の算出、集団間の形態学的分析を行う。 - 下顎大臼歯歯冠形態の分析
東京大学総合研究博物館の双生児歯型コレクションを利用し、大臼歯歯冠形態の3次元データを取得し形態特徴の遺伝性を分析する。 - 関東地方縄文遺跡出土の人骨タフォノミーの観察
廃屋墓出土人骨について、人骨表面のタフォノミー形質の観察を行う。
藤田 尚
2023年度は、2022年度に作成した生存曲線プログラミングを基に、現代人を含む諸国家および極めて確実性の高い過去集団の人口復元を目指す。これは、何度か述べている通り、「平均寿命」こそが、集団間の健康度の比較として最も優れた累積的ストレス指標であるからだ。ある遺跡のストレスマーカーや病変を調べ、その頻度を記載することは一次資料の蓄積という意味では重要であるが、これを以って集団間の健康度を比較することはできないか無意味に近い。例えば、現代日本人の60歳以上の方は、およそ半数が関節炎に罹患していると言われる。しかし、それは寿命が延びて長い生存期間を得た結果として、関節炎という病が出現したわけなのである。関節炎という一つのストレス指標でその集団の健康度を比較することは、ナンセンスであることが理解できるであろう。そのような視点からも、まず平均寿命の推定に全力を挙げるとともに、新手法を用いた感染症の特定が可能か、チャレンジする。原始・古代社会においては、感染症寄生虫症が死亡原因のトップであったことは間違いが無いが、いかんせん、その痕跡を骨から捉えることは困難であった。しかし、ゲノムサイエンスを始めとする新手法が発展してきていることから、そういった新手法が応用可能かどうかについても、検討を開始する。幸い、研究分担者(研究チーム)らは、多様な側面から研究を手掛けることが可能であるので、同僚研究者との連携を模索する。また、新生児や幼児の骨格は見つかることが稀なため、埋めガメその他幼少期の死者を具現化している事象に着目し研究を深化させていく。
米田 穣
2023年度は加曽利貝塚から出土した動物骨について、歯エナメル質のSr同位体比の測定をすすめる。その結果を現生植物と地質図を用いて作成した、高精度Sr同位体地図と比較して、妥当な動物生息域を復元できるかを検証する。もしも、Sr同位体比について妥当な結果をえることができれば、人歯でもエナメル質採取を検討する予定である。人歯エナメル質の分析は、動物骨で検証をすすめる加曽利貝塚と、古代ゲノム分析と同位体分析と実施している市原市の貝塚出土人骨を中心に準備をすすめる。
骨組織による動物遺体の処理方法についてさらに検討するために、埋葬されたイノシシと解体されたイノシシで骨組織像を比較して、解体されていない動物の骨が散乱骨に含まれている可能性を検討する。イヌは埋葬事例が多いため、散乱骨であっても解体された可能性はあまり考慮されていない。反対にイノシシは埋葬事例が少数であるため、散乱骨の多くは解体された食料残渣と考えられている。骨組織による新たな判定基準で、動物遺体にかかわる特殊な扱いが明らかにできるかもしれない。